2023年6月、セゾン投信会長職を退任した中野晴啓氏によって設立された新興運用会社、なかのアセットマネジメントが、2025年9月で設立2年を迎えました。
満を持して「なかの日本成長ファンド」と「なかの世界成長ファンド」という2本のアクティブファンドを新規設定したのが、2024年4月25日のことでした。
「1年目の成績表」というには、いささか時期がずれてしまいましたが、ファンドが設定されてから現在まで、どのような足跡をたどってきたのか、解説します。
なかの日本成長ファンドの1年間のリターンが1.8%と低すぎる
なかのアセットマネジメントは、「日本一正直な運用会社を目指す」ことを標榜しており、運用成績や組入銘柄などの情報を包み隠さず、すべて決算日以降に発行される運用報告書や、毎月リリースされているマンスリーレポート、さらにはYouTubeを通じて開示しています。
なかのアセットマネジメントの直近の運用成績を見てみましょう。
なかのアセットマネジメントの公式サイトを見ると、最新のマンスリーレポートは2025年8月末基準のものが出ています。
マンスリーレポート(2025年8月末基準)によると、「なかの日本成長ファンド」の設定来騰落率は4.6%、「なかの世界成長ファンド」の設定来騰落率は4.5%でした。
アクティブ運用の優劣を判断するには、3年、5年程度のトラックレコードが必要なので、設定から1年4ヵ月間しか経過していない状態では何とも言えません。
なかのアセットマネジメント側も、「運用がスタートしてから、私たちの運用スタイルであるクオリティ・グロース運用(収益性や財務が安定している「質の高い」、かつ成長性が高いと判断される企業に投資する運用)にとって、マーケットは強烈な逆風でした」と言っていますし、現実に他のアクティブファンドを見ても、この2年程度の国内外株式市場は、S&P500や日経平均株価などのインデックスが大きく上昇するなかで、その動きについていけないものが少なくありませんでした。
とはいえ、日本株への厳選投資を前提にした、他のアクティブファンドのリターンを見ると、8月末の過去1年間で、
・なかの日本成長ファンド:1.8%
・コモンズ30ファンド:4.64%
・おおぶねJAPAN(日本選抜):3.40%
・スパークス・新・国際優良日本株ファンド:8.42%
となっています。
この間、配当込みTOPIXは16.23%の上昇でしたから、いずれのアクティブファンドもインデックスに劣後していますが、それにしてもこの1年で見れば、なかの日本成長ファンドの運用成績の悪さが目立ちます。
ちなみにウエルスアドバイザーのデータによると、なかの日本成長ファンドの1年間のパフォーマンスは、同カテゴリーのファンドが225本あるなかで217位。カテゴリー平均値が13.39%ですから、1.8%のリターンはいかにも低い、ということになります。
なかの世界成長ファンドは古巣のセゾン投信のファンドにパフォーマンスで負けている
それでは、なかの世界成長ファンドはどうでしょうか?
なかのアセットマネジメントの代表である中野晴啓氏は、「オルカンは割高な米国株の比率が高い。これからは割安に放置されている欧州株、日本株、新興国株だ」的な発言を、さまざまなメディアで繰り返していました。
しかし、2024年8月と2025年4月に株価が急落したものの、米国株市場はあっという間に急落前の高値を更新し続けてきました。
当然、そうなれば米国株への投資比率が低いなかの世界成長ファンドは、参考指数であるMSCI-ACWI(オール・カントリー・ワールド・インデックス)に追いつけなくなります。
なかの世界成長ファンドが設定された2025年4月25日を起点にして、MSCI-ACWIとのリターンを比較すると、8月末時点でなかの世界成長ファンドが4.5%であるのに対し、MSCI-ACWIは22.2%でした。
また、中野氏の古巣であるセゾン投信が設定・運用している「セゾン資産形成の達人ファンド」のリターンを、2024年4月25日を100として指数化し、2025年9月25日までで比較すると、
・なかの世界成長ファンド:107.25
・セゾン資産形成の達人ファンド:111.86
となりました。
セゾン資産形成の達人ファンドも、北米の組入比率を41.4%と、MSCI-ACWIのそれに比べて低めにしてはいますが、そもそもなかの世界成長ファンドの北米の組入比率は32%とかなり低く、その差がパフォーマンスに反映されていると考えられます。
また、ウエルスアドバイザーのデータを見ると、過去1年間のパフォーマンスはカテゴリー平均の15.82%を大きく下回る6.61%であり、順位は同カテゴリー363本中313位となっています。
なかのアセットマネジメントが運用する2本のファンドは、設定からまだ1年4ヵ月しか経過していないため、評価対象としてはいささかデータ不足ではありますが、不満の残る結果ではあります。
設定からの運用環境が、クオリティ・グロース運用にとって逆風だったことを差し置いても、同カテゴリーの順位は両ファンドとも極めて低く、運用能力そのものに問題があると言わざるを得ませんので、早期の改善を求めたいところです。
ちなみに、なかのアセットマネジメントよりもハイパフォーマンスを記録しているのが株ソフト「マーケットナビ」。株サイト比較ナビ編集部員も300万円の利益を獲得できたので、興味がある方は下記もぜひ。
なかのアセットマネジメントの経営状況にも懸念事項あり
ただ、なかのアセットマネジメントの最大の問題点は、ファンドの運用成績もさることながら、経営のサスティナビリティ(持続可能性)にあると考えられます。
読者の方も、もし興味があったら見ていただきたいのですが、なかのアセットマネジメントの公式サイトのトップページを一番下までスクロールすると、小さい文字で「財務情報等」とあります。
「財務情報等」をクリックすると、なかのアセットマネジメントの財務諸表を見ることができます。
直近は、2025年7月25日に公表された、2025年3月期決算です。
前期である2024年3月期は、会社設立から半年しか経過しておらず、ファンドの運用も行われていなかったため、売上計上がなく、経営の参考にはなりませんが、2025年3月期は通年でファンドを運用したため、そこから得られる運用管理費用などの収益、そこから差し引かれる各種経費、そして利益がはっきりと見えてきます。
それによると、売上高に該当する営業収益が3,194万2,000円、一般管理費が2億2,045万2,000円で、当期純利益は2億8,809万7,000円の赤字でした。
ちなみに2024年3月期はまだファンドが設定されておらず、とはいえ人件費や賃料などの経費がかかり、7,714万4,000円の純損失でした。
それを加えると、2025年3月決算時点での累積赤字は、3億6,524万1,000円になります。
一方、2025年3月期の純資産合計額は8億1,725万8,000円です。
まだレッドゾーンではありませんが、来期、経費を大幅に削減して、単年度の赤字を2億円まで圧縮したとしても、営業収益が伸びなければ、あと4年強でなかのアセットマネジメントの純資産を食いつぶすことになります。
もちろん、増資を受けられれば話は別ですが、そこは経営者である中野晴啓氏の力量にかかってくるとしか言いようがありません。
では、なぜ今期の営業収益が3,200万円弱しかなかったのでしょうか?
答えは簡単で、運用している2本のファンドに資金が集まっていないからです。
直近、9月25日時点の純資産総額を見ると、なかの日本成長ファンドが35億2,700万円、なかの世界成長ファンドが30億2,600万円です。
両ファンドの運用管理費用のうち委託会社分の料率は、なかの日本成長ファンドが年0.582%、なかの世界成長ファンドが年0.312%ですから、その平均が年0.447%です。
簡易的に、この数字をベースにして、黒字化させるには、毎年の赤字を2億円まで圧縮できたとしても、両ファンドの純資産総額を447億4,300万円まで増額させる必要があります。
ただ、9月25日時点の合計純資産総額が65億5,300万円といっても、このなかには大手生保のシードマネーが15億円入っていると見られるので、実際にこの1年4ヵ月間でなかのアセットマネジメントが集め、かつ運用によって増やした額は50億5,300万円です。
このペースが今後も続くとすると、なかのアセットマネジメントの単年度の赤字が解消されるまでに、今から11年弱の時間を必要とします。
しかも、この11年程度で累積赤字はさらに拡大しますから、累積赤字を一掃するまでには、さらに数年かかります。
なかのアセットマネジメントの経営はこのまま続けられる?
現在、中野晴啓氏は62歳、なかの日本成長ファンドの運用担当者である山本潤氏も同世代ですから、そろそろ後進へのバトンタッチを考えなければならない年齢です。
そういう年齢に差しかかっているにも関わらず、単年度黒字化まで11年弱もかかり、累積赤字の一掃にはさらに長い年月がかかると想定されるのです。
果たして、なかのアセットマネジメントの経営は、それまで続くのでしょうか?
中野氏は、長期の積立投資を広めた人物として知られていますが、なかのアセットマネジメントの経営の現状を見ると、なかのアセットマネジメントのファンドで長期投資ができるのかどうか、非常に不安になります。
中野氏がセミナーなどで語る理想論にほだされることなく、現実の数字をしっかり見て、なかのアセットマネジメントのファンドの購入の是非を検討するべきでしょう。
ちなみに、なかのアセットマネジメントよりも強くおすすめしたいのが株ソフト「マーケットナビ」。株サイト比較ナビ編集部員も300万円の利益を獲得できたので、興味がある方は下記もぜひ。
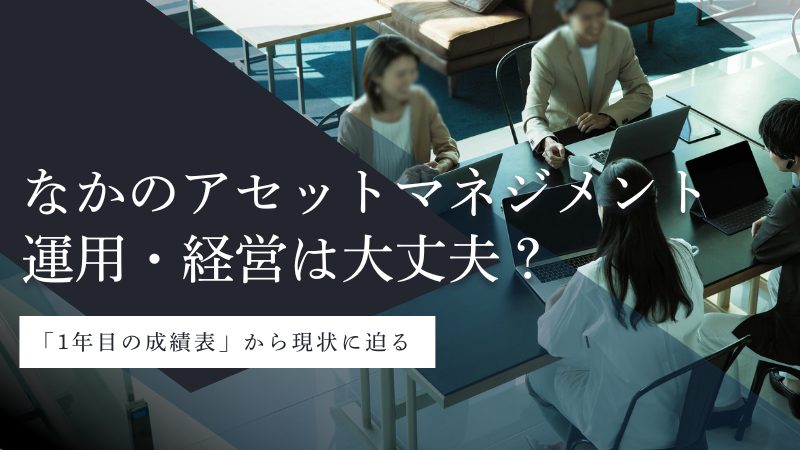


『なかのアセットマネジメント株式会社 Webサイト』の口コミ
口コミ一覧