株式投資を始めたい気持ちはあるものの、税金の金額や取り扱いがよくわからなかったりして、ためらっている人もいらっしゃることでしょう。
結論を先に言いますと、初心者の方は基本的に確定申告が不要な「NISA口座」と「特定口座(源泉徴収あり)」で株式投資をすることをおすすめします。
ただし、確定申告を行うことで節税できるケースもあるので、この記事を読んで理解を深めてくださいね。
株式投資の税金はいくら?税金の計算方法を解説
まずは、株式投資でかかる税金の税率と計算方法について解説します。
株式投資で得た利益の約20%が税金に
株式投資で利益が出ると、所得にかかわらず一律20.315%(=所得税および復興特別所得税15.315%+住民税5%)がかかります。
なお、詳しくは後述しますが、NISA口座を利用した場合は、株式投資で得た利益に税金はかかりません。
株式投資では譲渡所得(売却益)と配当所得(配当金)に税金がかかる
株式投資では主に下記の2つの利益に対して税金がかかります。
■譲渡所得(売買益):株価が安いときに購入して、株価が高いときに売却した際に出る利益
■配当所得(配当金):株式を一定期間保有することで配当金を得る場合に得られる利益
これらの利益に対して、20.315%の税金がかかるのです。
株式投資の譲渡所得の計算例
例えば、100株70万円で購入した株式の株価が上がり、100株100万円になったタイミングで売却すると、譲渡所得(売買益)30万円が発生します。
30万円の譲渡所得が出た場合、下記のように税金を計算します。
30万円×20.315%=税額6万945円
今回の株式投資で納める必要がある税金の金額は6万945円となるのです。
源泉徴収と確定申告とは何が違う?
株式投資の利益が出た場合には、源泉徴収または確定申告で納税します。
■源泉徴収:証券会社が利益にかかる税金を自動で差し引いて納税してくれる仕組み
■確定申告:1年間(1月1日~12月31日)の利益を税務署に申告し、自分で税金を納める方法
証券口座の種類によって、源泉徴収される口座と自分で確定申告をする口座があります。
株式投資の利益に影響大!?証券口座の基本知識
株式投資を始めるにあたって、どんな証券口座を選択して開設するかで、税金の納め方が異なってきます。
ここでは、証券口座の種類とその特徴について解説します。
株式投資ができる証券口座は3種類
株式投資ができる証券口座は以下の3種類です。
・特定口座(源泉徴収あり・源泉徴収なし)
・一般口座
・NISA口座
| 証券口座 の種類 | 特定口座 (源泉徴収あり ・源泉徴収なし) | 一般口座 | NISA口座 |
| 特徴 | 株式投資などの計算や 確定申告の手続きを 証券会社が簡略化してくれる口座 ※「源泉徴収あり」を選べば、 証券会社が利益にかかる税金を 自動で差し引いて納税してくれる | 株式投資などの計算や 確定申告の手続きは 利用者自身が行う口座 | 株式投資などから得られる利益 (売却益や配当金など)が 非課税になる口座 ※株式投資ができる NISAの「成長投資枠」は 年間240万円まで |
3種類の証券口座についてそれぞれ詳しく解説していきましょう。
特定口座(源泉徴収あり・源泉徴収なし):株式投資などの税額の計算や手続きを証券会社が簡略化してくれる
特定口座には、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。
源泉徴収ありを選択すると、投資で得られた利益にかかる税金を証券会社が差し引いて納税してくれるため、確定申告の手間を省けます。
源泉徴収なしを選択すると、投資により利益が出た場合は自分で確定申告を行う必要がありますが、譲渡(投資)による損益の計算を自分でする必要はありません。
なお、源泉徴収ありと源泉徴収なしのいずれを選択しても、特定口座内での譲渡にかかる1年間(1月1日から12月31日まで)の取引内容について、証券会社が「年間取引報告書」を作成してくれます。
一般口座:株式投資などの計算や確定申告の手続きは利用者自身が行う
一般口座は、自分で売買記録を管理・損益の計算をして、税務処理を自分で行う必要がある口座です。
一般口座だと、未公開株など特定口座で扱えない商品も保有できる魅力がありますが、税額の計算や確定申告の手間などがかかるので、投資初心者にはメリットが少ない口座といえます。
NISA口座:株式投資などから得られる利益(売却益や配当金)が非課税になる
NISA口座は、株式投資などから得られる利益にかかる税金(税率20.315%)が非課税になる口座です。
株式投資ができるNISAの「成長投資枠」は、年間240万円まで非課税で投資できます。
なお注意したいのが、NISA口座単独での開設はできないということです。
NISA口座はあくまで、特定口座か一般口座かの併用が必要になります。
投資初心者が保有するならどの口座がベスト?
初心者が株式投資を始める場合、NISA口座と特定口座(源泉徴収あり)の併用をおすすめします。
NISA口座は利益に対して税金がかからないのが大きな魅力なので、まずはNISA口座を優先して使うのをおすすめします。
株式投資で使えるNISAの成長投資枠(年間240万円)を使い切ってしまい、それよりさらに大きな額で株式投資にチャレンジしたい場合は特定口座(源泉徴収あり)を利用するとよいでしょう。
株式投資3つの節税テクニック
ここでは、株式投資を始める方に向けて、ぜひとも知っておきたい3つの節税テクニックをご紹介します。
1.NISAを活用:投資で得た利益(売却益・配当益)が非課税
NISA口座を利用すると、投資で得た利益(売却益・配当益)が非課税となります。
通常の投資だと、利益に対してかかる税金(税率20.315%)が自動的に非課税になるので、お得で便利です。
株式投資においてNISA口座の利用は、最も簡単な節税テクニックといえます。
2.損益通算を活用:株式投資で発生した損失を、他の株式の売却益や配当益と相殺して納税額を抑える
株式投資では損失を抱えるときもあります。
そんなときに「損益通算」を活用すれば、発生した損失を他の株式の売却益や配当益と相殺することで納税額を抑えることができます。
例えば、上場企業A社の株式投資で50万円の利益が出ていて、上場企業B社の株式投資で15万円の損失を抱えたとします。
その場合、A社での利益(50万円)からB社での損失(15万円)を差し引いた金額(35万円)に対して税金の計算をします。
| A社 | (利益) 50万円 |
| B社 | (損失) ▲15万円 |
| 損益通算 | (利益) 35万円 |
50万円の利益に対しては101,575円(=50万円×20.315%)の納税が必要になりますが、損益通算後の35万円に対してであれば約71,102円(=35万円×20.315%)になり、税負担を減らせます。
3.繰越控除を活用:株式投資で発生した損失を、翌年以降の利益と相殺して節税する
株式投資で発生した損失は、確定申告をすることにより翌年以降3年間は利益と相殺することができます。
例えば、2025年に株式投資で100万円の損失が発生し、確定申告をするとします。
そうすれば、2026年に30万円、2027年に40万円、2028年に30万円の利益が出たとしても、連続して確定申告をすれば利益に対する税金がかかりません。
| 2025年 | (損失) ▲100万円 | |
| 2026年 | (利益) 30万円 | ※繰越控除で30万円の利益に 対する税金は非課税に |
| 2027年 | (利益) 40万円 | ※繰越控除で40万円の利益に 対する税金は非課税に |
| 2028年 | (利益) 30万円 | ※繰越控除で30万円の利益に 対する税金は非課税に |
このケースで繰越控除を利用しないと、2026年~2028年の3年間で約20万円(=6万945円+8万1,260円+6万945円)を納税することになります。
・2026年:30万円×20.315%=6万945円
・2027年:40万円×20.315%=8万1,260円
・2028年:30万円×20.315%=6万945円
株式投資で損失を抱えたときには繰越控除を活用すべきといえます。
確定申告は必要?不要?知っておきたい4つのケース
ここでは、株式投資で確定申告が必要か不要かどちらのケースになるのか、知っておきたいケースについて解説します。
1.給与所得者は株式投資で年間20万円を超える利益が出る場合は確定申告が必要
年収2,000万円以下の給与所得者で株式投資などで20万円を超える利益が出ていて、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座を利用している場合は確定申告が必要になります。
ただし、特定口座(源泉徴収あり)やNISA口座で取引をしている場合は確定申告をする必要はありません。
監修者からひと言:副業をしている場合は要注意!
最近では本業以外に副業に力を入れている人も増えていますよね。
株式投資以外に副業などで所得がある場合、それらと合わせて20万円を超える利益を得ていたら確定申告をしなくてはいけません。
株式投資による利益は少なかったとしても、副業による所得と合算して利益が20万円を超える場合は、確定申告を忘れないように注意しましょう。
2.複数の証券会社を利用している場合は損益通算をして確定申告をする場合もある
複数の証券会社の口座を利用している場合、損益通算をして確定申告をするケースもあります。
例えば、証券会社A社の取引で10万円の利益、証券会社B社の取引で5万円の利益、証券会社C社の取引で7万円の利益が出ている場合、合算すると22万円(=10万円+5万円+7万円)の利益となります。
このようなケースで特定口座(源泉徴収なし)や一般口座を利用している場合、証券会社をまたいで損益通算を行い、確定申告をする必要があります。
3.特定口座(源泉徴収あり)を使い源泉徴収されすぎている場合は確定申告をすると還元される
例えば、証券会社A社の特定口座(源泉徴収あり)で50万円の利益が出ていて、証券会社B社の特定口座(源泉徴収あり)で25万円の損失があるとしましょう。
このケースだと、A社では50万円分の利益に対する税金が自動的に徴収されます。
しかし、損益通算すると利益及び損失は下記のようになります。
| A社特定口座 (源泉徴収あり) | (利益) 50万円 |
| B社特定口座 (源泉徴収あり) | (損失) ▲25万円 |
| 損益通算 | (利益) 25万円 |
損益通算をすると25万円(=50万円-25万円)の利益に対してだけ税金を支払えばよいことになります。
このようなケースでは、確定申告をすることでA社の取引で支払い過ぎた分の税金を還付してもらえるので確定申告をしたほうがお得です。
4.特定口座(源泉徴収なし)や一般口座を使い年間の利益が20万円以下の場合は確定申告が不要
特定口座(源泉徴収なし)や一般口座を使い、損益通算をしても年間の利益が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
確定申告の手続き方法
ここでは、確定申告の手続き方法について解説します。
確定申告における必要書類の記入と提出の流れ
株式投資で利益が出た場合の確定申告における必要書類は下記のとおりです。
| 書類名 | 内容 |
| 申告書 (第一表・第二表) | 所得税の申告書 |
| 申告書付表 (第三表) | 株式等の譲渡所得等を 記載するための付表 |
| 株式等に係る譲渡所得等の 金額の計算明細書 | 株式の取引内容がわかる書類 |
確定申告は毎年2月16日~3月15日まで(※土日祝の場合は翌営業日)に行う必要があります。
なお、以前は特定口座を利用している場合は「特定口座年間取引報告書」の提出が確定申告の際に必要でしたが、現在は国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行うことになったため、添付が不要になっています。
e-TAX(イータックス)で簡単に確定申告が可能
確定申告は、最寄りの税務署への郵送または持参による方法で行えますが、24時間自分の好きなタイミングで申告の手続きができる「e-TAX(イータックス)」の活用が便利です。
| e-TAX(イータックス) | 税務署への郵送・持参 | |
| メリット | ・パソコン/スマホで 24時間いつでも申請可能 ・還付までの時間が 通常の確定申告に比べて早い | ・特別な機器は不要 |
| デメリット | ・初期設定がやや複雑 (ID取得・認証など) | ・税務署の開庁時間しか申請できない ・郵送の場合は切手代がかかる |
e-Taxは初期設定がやや複雑ですが、還付までの時間が郵送・持参の場合と比較して早いといったメリットもあります。
また、確定申告の期限当日(3月15日)ギリギリまで申告の手続きができる点もe-Taxのメリットといえます。
まとめ:投資初心者は確定申告の手間が原則不要な方法を選ぶのがおすすめ!
投資初心者で確定申告などの手続きにめんどくささを感じるのであれば、原則、確定申告の必要がないNISA口座や特定口座(源泉徴収あり)をおすすめします。
NISA口座はそもそも利益にかかる税金が非課税ですし、特定口座(源泉徴収あり)は証券会社が自動的に税金を徴収してくれます。
ただし、特定口座(源泉徴収あり)を利用していて、年間の利益が20万円以下であれば確定申告をすることで税金の還付を受けられます。
手間に感じるかもしれませんが節税になるので、ぜひこのようなケースに該当する場合は還付を受けてくださいね。
なお、株式投資で口座を開くなら、簡単かつスピーディに口座開設ができるネット証券(SBI証券・楽天証券・松井証券・マネックス証券など)を選ぶことをおすすめします。
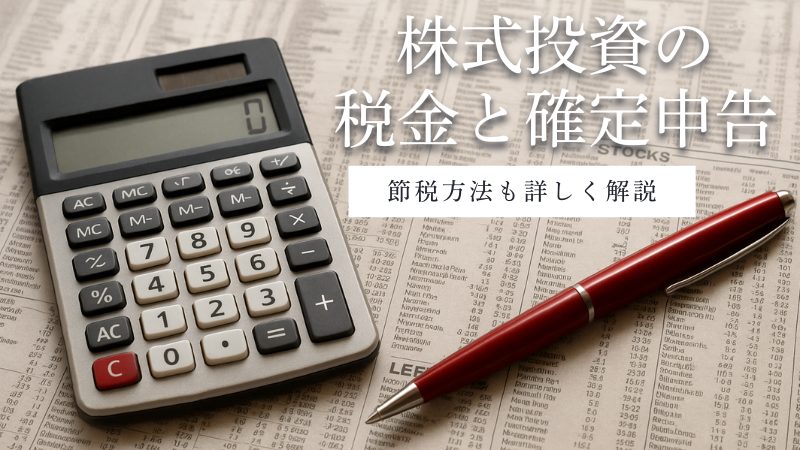

『』の口コミ
口コミ一覧